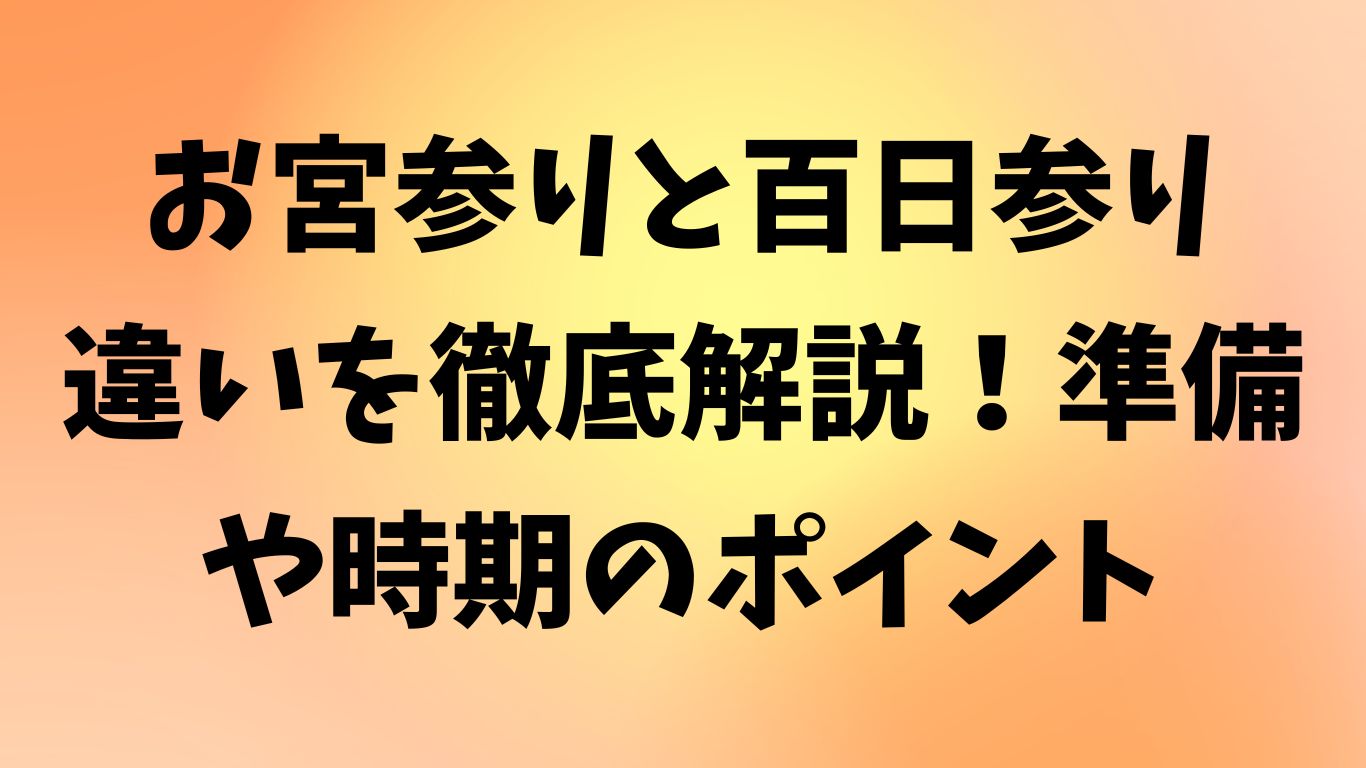お宮参りと百日参りの違いがわからない…
時期はいつがいいの?準備も気になるな。

初めての子育てで、大切な伝統行事。でも、ネットで調べてもいまいちよくわからなくて困っちゃいますよね。私も最初は本当に悩みました。
そこで今回は、お宮参りと百日参り違いを徹底解説!準備や時期のポイントについて紹介します。
- お宮参りと百日参りの違いは?時期や意味を徹底解説
- お宮参りの準備と流れを詳しく解説
- 百日祝いを楽しもう!準備と過ごし方
- お食い初めの準備と楽しみ方
この記事を読めば、お宮参りと百日参りの違いがはっきりわかります。赤ちゃんの大切な行事を楽しく準備しましょう。
お宮参りと百日参りの違いは?時期や意味を徹底解説
赤ちゃんの誕生は、家族にとって特別な瞬間です。
そして、生まれてきた赤ちゃんの健康と成長を祝う日本の伝統行事として、お宮参りと百日参りがあります。
でも、この二つの行事、何が違うの?いつやればいいの?と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
私自身、初めての子育てのときは本当に悩みました。
この記事では、お宮参りと百日参りの違いを徹底解説し、準備や時期のポイントをお伝えします。
新米ママやパパの皆さん、一緒に赤ちゃんの特別な日を迎える準備をしていきましょう!
お宮参りとは?由来と意味
お宮参りは、生まれた赤ちゃんを初めて神社やお寺に参拝させる日本の伝統行事です。
その起源は古く、平安時代にまで遡るといわれています。
当時は、子どもの mortality rate(死亡率)が高かったため、無事に生まれた喜びと、健やかな成長への願いを込めて行われるようになりました。
お宮参りの主な目的は、赤ちゃんの誕生を神様に報告し、健康と幸せな人生を祈願することです。
また、家族や親族が集まり、新しい家族の一員を社会に紹介する機会でもあります。



お宮参りは、赤ちゃんの人生の門出を祝う大切な行事なんですね。初めて親になった私たちにとっても、子育ての決意を新たにする素敵な機会になりそう!
一般的に、お宮参りの時期は以下のように決められています:
- 男の子:生後31日目(または32日目)
- 女の子:生後32日目(または33日目)
ただし、これはあくまで目安です。
赤ちゃんの健康状態や家族の都合に合わせて、生後100日以内に行うのが一般的です。
注意:赤ちゃんの体調が優れない場合は、無理せず延期することをおすすめします。
健康で穏やかな日を選ぶことが、何より大切です。
百日参りとは?100日目のお祝い
一方、百日参り(ももかざり)は、赤ちゃんの生後100日目を祝う行事です。
これは、お食い初め(おくいぞめ)とも呼ばれ、赤ちゃんが生まれてから100日間、無事に成長したことを祝う意味があります。
百日参りの主な目的は、赤ちゃんの健康な成長を祝福し、これからの人生が食べ物に困らないよう願うことです。
昔は、生後100日まで生き延びることが難しかった時代があり、この日を迎えられたことは大変喜ばしいことだったのです。



100日間、毎日愛情を込めて育ててきた成果を実感できる日ですね。赤ちゃんの成長を家族みんなで喜び合える、素敵な機会だと思います。
百日参りの行事内容は、地域や家庭によって多少異なりますが、一般的には以下のようなものがあります:
| 行事 | 内容 | 意味 |
|---|---|---|
| お食い初め | 赤ちゃんに食事を模擬的に与える儀式 | 一生食べ物に困らないよう願う |
| 歯固めの石 | 赤ちゃんの口に石を当てる | 丈夫な歯が生えるよう願う |
| お祝い膳 | 家族や親族で祝い膳を食べる | 赤ちゃんの成長を祝福する |
これらの行事を通じて、赤ちゃんの健康と成長を祝うとともに、家族の絆を深める機会にもなります。
100日参りの日付計算方法
100日参りの日付を正確に計算するのは、意外と難しいものです。
私も初めての子育てのとき、「えっ、生まれた日を含めるの?除くの?」とちょっと混乱しました。
実は、100日参りの計算方法には2つの考え方があるんです。
- 生まれた日を1日目として数える方法
- 生まれた翌日を1日目として数える方法
どちらの方法を選ぶかは、家庭や地域の習慣によって異なります。
ただし、最近では生まれた日を1日目として数える方法が一般的になってきています。
例えば、4月1日生まれの赤ちゃんの場合:
- 生まれた日を1日目とする場合:7月9日が100日目
- 生まれた翌日を1日目とする場合:7月10日が100日目
どちらの方法を選んでも、その日が都合が悪い場合は前後の日に調整しても問題ありません。
大切なのは、赤ちゃんと家族みんなが穏やかに過ごせる日を選ぶことです。



100日目の計算、意外と悩むポイントですよね。私の場合は、生まれた日を1日目として数えましたが、どちらでも大丈夫です。赤ちゃんの100日間の成長を祝える日なら、1日や2日のズレは気にしなくていいんですよ。
お宮参りと百日祝いどちらで撮影する?
赤ちゃんの成長を記念に残したい!そう思ったとき、お宮参りと百日祝い、どちらで写真撮影をするべきか迷うことがありますよね。
実は、両方とも素敵な思い出になるので、可能であれば両方で撮影することをおすすめします。
でも、時間やコストの関係で一方しか選べない…そんなときは、それぞれの特徴を踏まえて選んでみましょう。
- お宮参り:赤ちゃんが小さく、祝い着姿が愛らしい
- 百日祝い:表情が豊かになり、笑顔が増える
お宮参りの撮影では、赤ちゃんの小さくてかわいらしい姿を祝い着姿で残せます。
一方、百日祝いの撮影では、生後3ヶ月を過ぎた赤ちゃんの成長した姿や、豊かな表情を捉えることができます。
どちらを選ぶにしても、赤ちゃんの貴重な姿を残せるのは間違いありません。
私の経験から言えば、お宮参りの写真は伝統的な雰囲気が素敵で、百日祝いの写真は赤ちゃんの成長を感じられて嬉しかったです。



写真選びに正解はありません。家族で相談して、自分たちが一番残したい瞬間を選んでくださいね。どちらも素敵な思い出になること、間違いなしですよ!
お宮参りの準備と流れを詳しく解説
お宮参りは赤ちゃんにとって初めての大切な行事。
でも、初めての親にとっては何を準備すればいいのか、当日はどんな流れなのか、不安になることもありますよね。
私も初めてのときは、本当に戸惑いました。
ここでは、お宮参りの準備から当日の流れまで、詳しく解説していきます。
お宮参りの服装選びのポイント
お宮参りの服装選びは、多くの親御さんが悩むポイントの一つです。
赤ちゃんの服装はもちろん、両親や祖父母の服装にも気を配る必要があります。
基本的に、お宮参りは「晴れ着」を着る機会です。
ただし、あまり凝りすぎず、赤ちゃんと家族が快適に過ごせる服装を選ぶことが大切です。
- 赤ちゃん:祝い着(産着)を着用
- 母親:着物やワンピース(華美すぎないもの)
- 父親:スーツやジャケットスタイル
- 祖父母:和装や控えめな洋装
赤ちゃんの祝い着は、レンタルや購入、お下がりなど、家庭の事情に合わせて選びましょう。
母親の服装は、和装なら訪問着や色無地、洋装ならワンピースやスーツが一般的です。
父親は、スーツやジャケットスタイルが基本です。
注意:赤ちゃんを抱っこする際に滑りやすい素材の服は避けましょう。



服装選びは楽しみながらも、赤ちゃんの安全と快適さを第一に考えてくださいね。私の経験上、着脱しやすく、赤ちゃんの動きを制限しないものが一番おすすめです!
お宮参りの当日の流れ
お宮参りの当日は、どんな流れで進むのでしょうか。
初めての方は、きっと緊張すると思います。
でも、基本的な流れを知っておけば、安心して臨むことができますよ。
お宮参りの基本的な流れは、「参拝」「お祓い」「記念撮影」の3つです。
具体的には、以下のような流れになります。
| 順番 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 神社に到着 | 鳥居をくぐる前に軽く会釈 |
| 2 | 手水舎で手を清める | 赤ちゃんは省略可能 |
| 3 | 参拝 | 二礼二拍手一礼が基本 |
| 4 | お祓い | 神主さんのお祓いを受ける |
| 5 | 記念撮影 | 境内や鳥居前で撮影 |
| 6 | 直会(なおらい) | 家族や親族での食事会(任意) |
参拝の作法は神社によって多少異なりますが、一般的には「二礼二拍手一礼」が基本です。
ただし、赤ちゃんを抱っこしているので、無理のない範囲で行いましょう。
お祓いの際は、神主さんの指示に従ってください。
赤ちゃんが泣いても慌てる必要はありません。神様に元気な声を聞かせているんだと思えば大丈夫です。



お宮参りの流れ、意外とシンプルでしょう?私も初めは緊張しましたが、神主さんが丁寧に教えてくれるので安心でしたよ。赤ちゃんと一緒の大切な時間を楽しんでくださいね!
お宮参りのお祝い金の相場
お宮参りに際して、祖父母や親戚からお祝い金をいただくことがあります。
また、神社へのお礼や、写真撮影の費用など、お金に関する疑問も多いですよね。
ここでは、お宮参りに関連するお金の相場について、簡単にまとめてみました。
- 祖父母からのお祝い金:1〜5万円程度
- 親戚からのお祝い金:5千円〜3万円程度
- 神社へのお礼:5千円〜1万円程度
- 写真撮影費用:2〜5万円程度(スタジオによる)
これらの金額はあくまで目安です。
家庭の事情や地域の慣習によって異なることもあります。
大切なのは、気持ちを込めて赤ちゃんの健やかな成長を祝うことです。
お祝い金をいただいた場合は、必ずお礼状を送りましょう。
赤ちゃんの写真を同封すると、より喜ばれます。



お金の話って難しいですよね。でも、みんな赤ちゃんの幸せを願っているんです。金額にこだわりすぎず、感謝の気持ちを大切にしましょう。お礼状書きは大変でしたが、後から「可愛い写真をありがとう」と言われて嬉しかったです!
百日祝いを楽しもう!準備と過ごし方
赤ちゃんが生まれて100日。
あっという間だったような、長かったような…。
この大切な節目を、家族みんなで楽しく祝いましょう。
ここでは、百日祝いの準備と楽しみ方についてお話しします。
百日祝いのメニューと食事会
百日祝いの中心となるのが、お食い初めの儀式です。
赤ちゃんに食べ物を擬似的に食べさせる儀式で、一生食べ物に困らないようにという願いが込められています。
お食い初めには、決まったメニューがあります。これを「お食い初め膳」と呼びます。
- お赤飯(幸せの象徴)
- お吸い物(健康長寿の願い)
- 鯛(めでたい)
- 小魚(知恵がつくように)
- 野菜の煮物(健康を願って)
- 果物(甘い人生を)
これらのメニューは、自宅で準備することもできますし、専門店やホテルなどでセットを注文することもできます。
家族の状況に合わせて、無理のない方法を選びましょう。
注意:赤ちゃんに実際に食べさせるわけではありません。あくまで儀式ですので、安全面に十分注意してください。
お食い初めの後は、家族や親族で食事会を楽しむのが一般的です。
この機会に、赤ちゃんの100日間の成長を振り返ったり、今後の子育ての話をしたりするのもいいですね。



お食い初め、私も最初は緊張しましたが、家族みんなで赤ちゃんの成長を喜び合えて本当に素敵な時間でした。準備は大変かもしれませんが、きっと素敵な思い出になりますよ!
100日参りに行く神社の選び方
100日参り(百日参り)は、必ずしも神社に行く必要はありませんが、お宮参りと兼ねて行う家庭も多いです。
では、どんな基準で神社を選べばいいのでしょうか?
100日参りの神社選びのポイントは、アクセスの良さと赤ちゃんの安全性です。
- 自宅や実家から近い神社
- 駐車場があるか、公共交通機関でアクセスしやすい神社
- 授乳室やおむつ替えスペースがある神社
- バリアフリー対応(ベビーカーで移動しやすい)の神社
- 子育てにご利益があるとされる神社
特に決まりはないので、家族にとって便利で思い入れのある神社を選びましょう。
例えば、両親が結婚式を挙げた神社や、地元の有名な神社など、家族の歴史に関連した場所を選ぶのも素敵ですね。
また、事前に神社に連絡を入れて、100日参りの受け入れ態勢を確認しておくとより安心です。



私たちは、結婚式を挙げた神社に100日参りに行きました。思い出の場所で赤ちゃんの成長を祝えて、とても感慨深かったです。でも、近場の神社でも十分素敵な思い出になりますよ。大切なのは家族の気持ちです!
100日参り時の神社へのお金の相場
100日参りで神社にお参りする際、お金に関する疑問がつきものです。
いくら渡せばいいの?どんな形式で渡すの?など、悩む方も多いでしょう。
100日参り時の神社へのお礼は、一般的に5,000円〜10,000円程度が相場です。
ただし、これはあくまで目安で、神社の規模や地域の慣習によって異なる場合があります。
- 金額:5,000円〜10,000円程度
- 形式:新札を水引きでくるんだもの(御初穂料)
- 渡し方:神主さんに直接手渡し、または賽銭箱へ
- 追加費用:御守りや御札を購入する場合あり
御初穂料(おはつほりょう)は、神社によっては受付で準備できる場合もあります。
事前に神社に確認しておくと安心ですね。
注意:お金以上に大切なのは、感謝の気持ちです。金額にこだわりすぎず、心を込めてお参りしましょう。
また、100日参りの際に赤ちゃんの名前を神社に奉納する「命名式」を行う場合は、別途費用がかかることがあります。
これについても、事前に神社に確認しておくといいでしょう。



お金の話って難しいですよね。でも、神主さんはとても親切で、分からないことがあれば丁寧に教えてくれますよ。私も最初は緊張しましたが、赤ちゃんの健康を祈る気持ちを大切に、素直な気持ちでお参りしました。きっと、皆さんも素敵な思い出になると思います!
お食い初めの準備と楽しみ方
お食い初めは、赤ちゃんの健やかな成長を祝う大切な行事です。
でも、初めての方にとっては、何を準備すればいいのか、どう進めればいいのか、不安になることもあるでしょう。
ここでは、お食い初めの準備から楽しみ方まで、詳しく解説していきます。
お食い初めの意味と時期
お食い初めは、赤ちゃんの人生で初めて食事をする儀式を模した行事です。
実際に食べさせるわけではありませんが、一生食べ物に困らないようにという願いが込められています。
お食い初めの意味は、赤ちゃんの健康と成長を祝福し、豊かな食生活を願うことです。
時期については、一般的に生後100日頃(3ヶ月過ぎ)に行われます。
ただし、厳密に100日目でなくても構いません。
- 男の子:生後110日頃
- 女の子:生後100日頃
これはあくまで目安で、家族の都合に合わせて前後しても問題ありません。
大切なのは、家族みんなで赤ちゃんの成長を祝う気持ちです。
注意:赤ちゃんの体調が優れない場合は、延期することをおすすめします。無理をせず、赤ちゃんと家族が楽しめる日を選びましょう。



お食い初めの日程、最初は「ピッタリ100日目じゃないとダメかな?」って悩みました。でも、家族みんなが集まれる日を選んだら、とても温かい雰囲気になりましたよ。赤ちゃんの笑顔を見ながら、みんなで食事を楽しむ。そんな時間が何より大切だと思います。
お食い初めの準備リスト
お食い初めの準備は、意外と細かいものが多いんです。
私も初めてのときは「あれ?これも必要だったの?」ということがちょくちょくありました。
でも、事前に準備リストがあれば安心ですよね。
お食い初めの準備に必要なものは、大きく分けて「食事関連」と「儀式関連」の2つです。
- 食事関連
- お食い初め膳(レンタルや購入)
- 赤飯
- お吸い物
- 焼き鯛
- 野菜の煮物
- 果物
- 儀式関連
- 歯固めの石
- 箸(かわいい柄のもの)
- 赤ちゃんの晴れ着
- 記念写真用の小物
お食い初め膳は、専門店やデパートでレンタルや購入ができます。
時間や予算に余裕がある場合は手作りするのも素敵ですね。
歯固めの石は、赤ちゃんの歯が丈夫に育つようにという願いを込めて使います。
小さな白い石を用意しましょう。
注意:歯固めの石を実際に赤ちゃんの口に入れるのは危険です。赤ちゃんの頬に軽く当てる程度にしましょう。



準備リスト、最初は「こんなにいるの!?」って驚きました。でも、一つ一つ用意していくうちに、だんだんワクワクしてきたんです。特に赤ちゃんの晴れ着選びは楽しかったですよ。みなさんも、準備を楽しみながら、素敵なお食い初めの日を迎えてくださいね。
祖父母を交えたお食い初めの過ごし方
お食い初めは、家族みんなで赤ちゃんの成長を祝う素敵な機会です。
特に、祖父母を交えて行うと、より思い出深いものになりますよ。
祖父母を交えたお食い初めでは、世代を超えた家族の絆を深められます。
ここでは、祖父母と一緒に楽しむお食い初めの過ごし方をご紹介します。
- 祖父母に儀式の一部を担当してもらう
- 家族の歴史や伝統を語り合う時間を設ける
- 赤ちゃんと祖父母の記念写真を撮影
- 祖父母から赤ちゃんへのメッセージを書いてもらう
- 家族で手作りした料理を一緒に楽しむ
例えば、お食い初めの儀式で、祖父に「歯固めの石」を赤ちゃんに当ててもらったり、祖母に赤ちゃんに箸を持たせてもらったりするのもいいですね。
また、食事の際に、両親や祖父母の子供時代の思い出話を聞くのも楽しいでしょう。
家族の歴史を知ることで、赤ちゃんの存在がより一層特別なものに感じられるでしょう。
注意:祖父母の方々にも無理のない範囲で参加してもらいましょう。
長時間の行事で疲れてしまわないよう、適度な休憩時間も設けるといいですね。



私たち家族のお食い初めでは、祖父母に赤ちゃんへのメッセージカードを書いてもらいました。将来、赤ちゃんが大きくなったときに読み返せるよう、アルバムに大切に保管しています。きっと素敵な思い出になりますよ。
お食い初めは、単なる儀式ではありません。
家族の絆を深め、赤ちゃんの成長を皆で喜び合う、かけがえのない時間なのです。
祖父母を交えることで、より豊かな経験になることでしょう。
赤ちゃんにとっても、家族みんなに愛されていることを感じる特別な日になるはずです。
お食い初めの準備は大変かもしれません。
でも、その分だけ思い出深いものになります。
ぜひ、家族みんなで協力して、素敵なお食い初めを迎えてくださいね。
きっと、かけがえのない家族の思い出になるはずです。



お食い初め、本当に素敵な思い出になりました。赤ちゃんの笑顔、家族みんなの温かい雰囲気、全てが宝物です。みなさんも、準備は大変かもしれませんが、きっと素晴らしい経験になると思います。赤ちゃんの健やかな成長を願いながら、家族で楽しい時間を過ごしてくださいね。
お宮参りと百日参り、そしてお食い初め。
これらの行事は、赤ちゃんの成長を祝う大切な機会です。
それぞれに意味があり、家族の絆を深める素晴らしい時間となります。
準備や進め方に悩むこともあるかもしれません。
でも、完璧を求める必要はありません。
大切なのは、家族みんなで赤ちゃんの成長を喜び、愛情を込めて祝福することです。
この記事が、皆さんの素敵な思い出作りの一助となれば幸いです。
赤ちゃんの健やかな成長と、家族の幸せを心からお祈りしています。
お宮参りと百日参り違いを徹底解説!準備や時期のポイント【まとめ】
この記事では、お宮参りと百日参りの違いについて解説してきました。
- お宮参りと百日参りの違い
- それぞれの準備と流れ
- 赤ちゃんの成長を祝う方法
お宮参りと百日参りは、赤ちゃんの成長を祝う大切な行事です。それぞれの意味や時期、準備の違いを理解することで、思い出に残る祝い事になります。
家族や親戚と相談しながら、赤ちゃんの成長をゆっくり楽しむことが大切です。記念写真を撮ったり、特別な食事を用意したりして、素敵な思い出を作りましょう。



赤ちゃんの成長を祝う行事がこんなにたくさんあるなんて知らなかったわね
お宮参りと百日参りを通じて、赤ちゃんの健やかな成長を祝い、家族の絆を深めていきましょう。